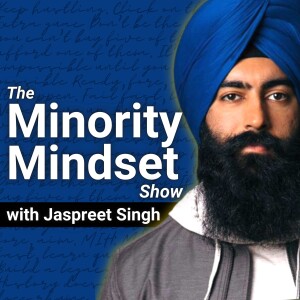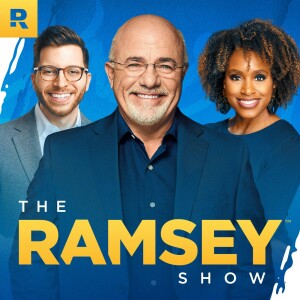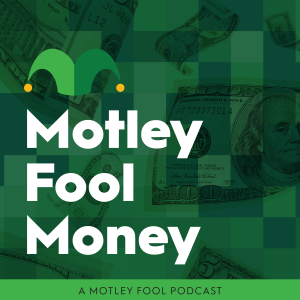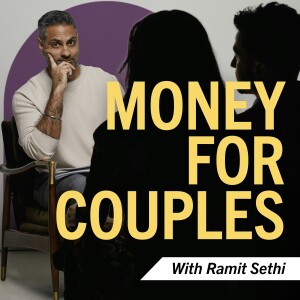REINAの「マネーのとびら」(日経電子版マネーのまなび)
https://anchor.fm/s/642771a8/podcast/rssEpisode List

不動産、売却時の税率は5年超、10年超で大きな差が
日経電子版「マネーのまなび」のPodcastです。アメリカ出身タレントのREINAさんがリスナーと一緒にお金のイロハを学んでいきます。解説は日本経済新聞 金融・市場ユニット所属で動画「マッスルマネー学園」に出演する露口一郎です。 今回のテーマは「不動産売却時の税金」です。都心部を中心に不動産価格、特にマンション価格が上昇しており、あまりの値上がりぶりに売却を考える人も増えていそうです。ただし、売却時には保有期間に注意を払わないと税金が大きく違ってきます。 都心部のマンションは新築だけでなく、中古の価格も高騰しています。不動産調査会社の東京カンテイ(東京・品川)の資料によれば、6月の中古マンション平均希望売り出し価格は、東京都心6区(千代田・中央・港・新宿・文京・渋谷)で前月比1.1%高い「70㎡あたり1億2058万円」でした。上昇は17カ月連続です。 中古マンションでもここまで上昇すれば売りたくなるのは当然です。でも、ちょっと待ってください。不動産は保有期間によって譲渡所得(売却益)に対する税金が大きく異なります。売却する年の1月1日時点で保有期間が5年以下だと、所得税や住民税などを合わせた税率は39.63%です。つまり売却益の4割は税金として払う必要が出てきます。 一方で保有期間が5年を超えれば、税率は20.315%に低下します。REINAさんは「税率にかなり差がありますね。2倍近いじゃないですか」と驚いていました。このほか、番組では自宅売却時の特例(3000万円特別控除や、10年超保有の自宅を売却する際の14.21%の軽減税率)についても取り上げています。自宅を売るなら最低でも5年、できれば10年は持ちたいところです。 番組後半は「Playback〜思い出のあの年」。今回は1988年です。この年、日経平均株価は初めて3万円台に乗せました。長らく抜けなかった89年末の3万8915円に向かって突き進んだ年で、世間はバブルまっただ中。日産自動車が発売した高級自動車「シーマ」は爆発的な人気となりました。 現在はパリオリンピックが開かれていますが、この年はソウルオリンピックの開催年でした。オリンピックが人々に感動を与えるのは今も昔も変わりません。マッスルマネー学園の露口学園長は当時高校生で、ソウルオリンピックにかなりの影響を受けました。金メダルを5個獲得したアメリカのマット・ビオンディ選手に憧れ、大学入学と同時に「オリンピックに出よう」と水泳部に入部したのです。ところが現実は甘くありません。あまりに厳しい練習が待っていたため、露口のオリンピック出場の夢は露と消え……。なおREINAさんは、時間的にリアル視聴の難しいパリオリンピックを録画で観戦しているそうです。日本選手の一層の活躍を期待していました。 なお今回のマンション売却時の税金や手続き、注意点について、さらに詳しく知りたい方はこちらの日経電子版の関連記事もお読みください。 ■中古高騰、自宅マンション売るなら? 税・手数料に注意

腕利きが使う3つの株価指標 夏枯れ相場で有望株仕込む
日経電子版「マネーのまなび」のPodcastです。アメリカ出身タレントのREINAさんがリスナーと一緒にお金のイロハを学んでいきます。解説は日経マネー編集長の中野目純一です。 今回のテーマは「実力者の銘柄選定術」です。8月以降の日本株相場はどんな展開になりそうなのか、腕利きの個人投資家たちは有望株をどう探し出しているのかを解説します。 日本株相場は6月中旬から再び活況となり、日経平均株価は7月11日には史上初めて4万2000円台に乗りました。ところが、そこから一転して下落の一途をたどり、7月25日には3万8000円を割り込みました。中野目編集長は「夏枯れ相場」というアノマリー通りの展開になってきていると説明します。アノマリーとは、確たる理由はないけれどもよく起きる経験則のことです。日本株市場では例年7月中旬以降に売買が細り、軟調になることが多く「夏枯れ相場」と呼ばれます。 この展開はデメリットばかりではなく、高くて買えなかった銘柄の価格も下がるため、手ごろな価格で仕込むチャンスにもなります。ただ、問題は値上がりが期待できる有望株をどう見つけ出すかです。そこで中野目編集長は、腕利きの個人投資家が銘柄選びで活用している3つの株価指標を紹介。REINAさんも億万投資家の実践例に聞き入っていました。3つの株価指標の具体的な内容や特徴、留意点を番組で確認していきましょう。 番組後半は「Playback〜思い出のあの年」。今回は2002年です。この年、日本ではデフレ不況が深まり、日経平均株価はバブル崩壊後の最安値を更新して、9000円を割り込む局面もありました。輸入牛肉の国産偽装などの企業不祥事も相次いで発覚。一方、アメリカではイラク情勢をめぐる緊迫が深まり、北朝鮮の核開発疑惑やインドネシア・バリ島の爆弾テロなど、国内外で暗いニュースが続いた1年でした。そうした中で日本国民を勇気づけた明るい話題が、サッカーワールドカップでの日本代表の決勝トーナメント進出と、東大名誉教授の小柴昌俊さんと島津製作所の研究者、田中耕一さんのノーベル賞受賞でした。 中野目編集長はこの年の12月に結婚。さらに7月に当時所属していた土木技術者向け情報誌「日経コンストラクション」の記者として初めて海外出張に出向くなど、公私ともに大きな節目となった1年だったそうです。欧州各国を巡った新婚旅行のエピソードに「すごいですねぇ」とREINAさんも目を丸くしていました。 なお今回の「実力者の銘柄選定術」について、さらに詳しく知りたい方はこちらの日経電子版の関連記事もお読みください。 ■銘柄間のPER比較は危険? 正しく使うコツを覚えよう ■資産3億円の会社員投資家 中小型の有望IPO株に的を絞る

勝てる投資家の特徴とは? 新NISAの利用実態も明らかに
日経電子版「マネーのまなび」のPodcastです。アメリカ出身タレントのREINAさんがリスナーと一緒にお金のイロハを学んでいきます。解説は日経マネー編集部の田中創太です。 今回のテーマは「勝てる投資家の特徴」です。これは日経マネーが毎年春に実施している「個人投資家調査」の結果をもとにしたもので、今年の調査には昨年より4000人も多い約1万2000人の声が寄せられました。新NISA(少額投資非課税制度)が始まり日本全体で投資熱が高まる中、どうすれば勝てる投資家になれるのでしょうか。 今年は投資歴が6カ月未満の初心者の割合が増え、全体の12%になりました。新NISAについては初心者を含め、回答者の約9割が「既に活用している」と回答。値上がり益や配当に税金がかからない長所を意識し、「新NISAは活用しないと損だ」と考えている人が多いということでしょう。 新NISAの非課税投資枠は、つみたて投資枠が年120万円、成長投資枠が年240万円です。番組では、個人投資家がそれぞれの枠で年内にいくらくらい投資しようとしているのか、月収の何割くらいを投資に回しているのかといったリアルなデータを紹介しました。中には「枠は全て使い切る。NISAに投資しすぎて生活が質素になった」という人もいるようです。 さらに、若者とシニア世代では「投資する理由」がかなり違うということや、昨年の上昇相場の中でも大きく勝てた投資家は意外に少なかったこと、2021年以降に資産を毎年20%以上増やしている「勝ち組投資家」の投資スタイルなどについても解説しました。特に勝ち組から投資初心者へのアドバイスは必聴です。 番組後半のコーナー「Playback〜思い出のあの年」は、今回は2020年です。皆さんもご記憶の通り新型コロナウイルスの感染拡大が始まった年ですが、田中はちょうど大学を卒業して、新卒で入社した時期でした。卒業旅行中にイタリアが入国制限をし始めて慌てて旅程を変更した話や、コロナ禍中の新人記者時代のエピソードを話しました。たった4年前なのに、既にちょっと懐かしくもあるコロナ禍初期について、REINAさんと振り返っています。 なお今回の「日経マネー個人投資家調査2024」について、さらに詳しく知りたい方はこちらの日経電子版の関連記事もお読みください。 ■「資産1億円超」20人に1人 30代前半で達成した人も ■「勝ち組」の投資家が愛用 投資に役立つ便利なITツール

キャッシュレス時代のお小遣い教育 上手なやり方は?
日経電子版「マネーのまなび」のPodcastです。アメリカ出身タレントのREINAさんがリスナーと一緒にお金のイロハを学んでいきます。解説は日本経済新聞の安田亜紀代です。 今回のテーマは「いまどきのお小遣い教育」です。キャッシュレス決済の普及率が約4割に迫り、買い物が便利になる一方で、子どもたちが金銭感覚を身につけるのが難しくなっています。QRコードや電子マネーなどを利用したキャッシュレス決済は現金を直接やり取りしないため、「お金が減る」という実感を得にくくなっています。従って特に子どもが小学生のうちは、小遣いはまず現金で渡し、お金の大切さややり繰りを学ぶことから始めることが大切です。 とはいえ、子どもたちが大人になる頃には、今以上にキャッシュレス決済が普及しているでしょう。早いうちに慣れさせたいと考えている親も多いはずです。キャッシュレスに慣れつつ、お金の管理について学べる便利なツールとして、最近は親子向けのプリペイドカードのサービスが出てきています。具体的なサービスとしては三井住友カードの「かぞくのおさいふ」や、シャトル(東京・港)が提供する「シャトルペイ」などがあります。番組ではこれらのサービスの特徴のほか、デビットカードやクレジットカードなどを家計簿アプリの「マネーフォワードME」と連携させて子どもの自立を促している家庭の事例も紹介しています。 番組後半のコーナー「Playback〜思い出のあの年」は、今回は2011年です。東日本大震災があったこの年、安田は入社5年目の企業取材担当記者。過去最大の円高、1ドル=75円32銭をつけ、製造業は打撃を受けました。しかし安田が担当していたエンタメ業界は意外にも好調で、知的財産(IP)に関するビジネスモデルの面白さを知った時期でした。当時アメリカでも人気を集めていた「ハローキティ」ブームなどの話題でREINAさんと盛り上がりました。 なお今回の「お小遣い教育」について、さらに詳しく知りたい方はこちらの日経電子版の関連記事もお読みください。 ■お金の教育、まず現金で 「使うと減る」で見直し促す

為替介入は「密室の駆け引き」? 円安抑制策は何か
日経電子版「マネーのまなび」のPodcastです。アメリカ出身タレントのREINAさんがリスナーと一緒にお金のイロハを学んでいきます。解説は日本経済新聞編集委員の小栗太です。 今回のテーマは「為替介入について学ぼう」です。歴史的な円安への歯止め役として注目されている政府・日銀の円買い介入。ただ具体的な政策の中身については「密室の駆け引き」と呼ばれるほど、あまり知られていません。最近は新NISAを利用して、外貨資産に投資している人も少なくないと思います。突然の大規模な円買い介入で円高基調に転換し、思わぬ為替差損を被らないよう、基本を学んでおきましょう。 番組では、なぜ為替介入が必要とされるのかを整理したうえで、市場関係者から為替介入が「密室の駆け引き」と呼ばれる理由を探りました。為替介入は経済や金融に大きく影響する政策なので、あらかじめ主要国の間で約束事があること、政策効果を高めるために秘密裏に実行されやすいことなどがポイントです。 そのうえで、為替介入以外に円安を止める方法がないのかについても考えました。例えば日本企業が海外に移した工場などの生産拠点を再び国内に戻して輸出を増やすこと、インバウンド(訪日外国人)需要の拡大に合わせて日本の製品やサービスを売り込むことなどを議論。日本のアニメやゲームなどのコンテンツ産業を新たな輸出品として海外に売り込むといった意外なアイデアも登場します。 番組後半の「Playback〜思い出のあの年」では、2013年を取り上げました。この年は安倍晋三政権の経済政策、アベノミクスの下で、日銀が異次元緩和と呼ばれる大規模な金融緩和に乗り出した年です。小栗はちょうど13年夏からニューヨークのビジネススクールに通い始めており、学内の研究者からアベノミクスや異次元緩和について議論したいと、多くの誘いを受けたエピソードを披露。REINAさんもハーレムにあったクリントン元大統領の事務所でインターン経験があり、ハーレムのレストランの話題でも盛り上がりました。 なお今回の「為替介入」について、さらに詳しく知りたい方はこちらの日経電子版の関連記事もお読みください。 ■長引く「円弱」時代 転機は秋の日米中銀会合か ■マネーの知識ここから~外貨投資編
Create Your Podcast In Minutes
- Full-featured podcast site
- Unlimited storage and bandwidth
- Comprehensive podcast stats
- Distribute to Apple Podcasts, Spotify, and more
- Make money with your podcast