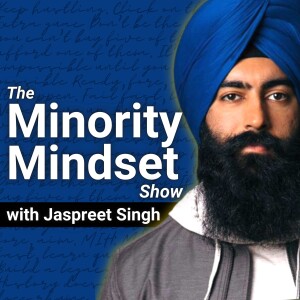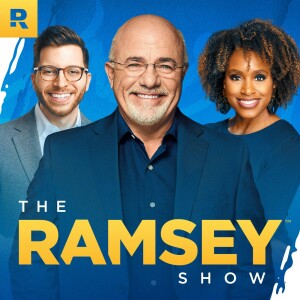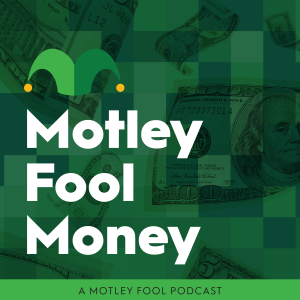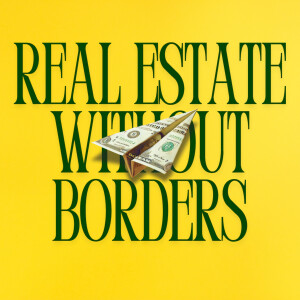REINAの「マネーのとびら」(日経電子版マネーのまなび)
https://anchor.fm/s/642771a8/podcast/rssEpisode List

賃貸の火災保険、保険金額や補償内容の見極めで節約も
日経電子版「マネーのまなび」のPodcastです。アメリカ出身タレントのREINAさんがリスナーと一緒にお金のイロハを学んでいきます。解説は日本経済新聞の岸田幸子です。今回のテーマは「賃貸住宅の火災保険」です。この春に賃貸住宅に引っ越した人は、賃貸借契約と同時期に、火災保険にも加入したのではないでしょうか。仲介する不動産会社に勧められるものを選ぶ人は多いですが、必ずしも指定の火災保険に入る必要はありません。個人が火災保険を選ぶ際のポイントや注意点について学びましょう。賃貸住宅向けの火災保険は主に、「家財補償」「個人賠償責任補償(個賠責)」「借家人賠償責任補償」で構成されています。入居者にとって重要なのは家財補償と個賠責です。家財補償は家具や衣類が損害を受けた時に、契約で決めた保険金額を上限に、同じ程度の新品を買い直す費用や修理費用を受け取れます。保険金額は損害額以上は出ないので、高額に設定しすぎると保険料が無駄になってしまいます。個賠責は第三者に損害を与えたときの補償で、洗濯機が壊れて下の階を水浸しにしたなどの損害賠償に活用できます。ただし個賠責は自動車保険などに付いている可能性があるので、まずは既に加入している保険の補償内容を確認するのが大切です。番組後半の「My favorite〜私の推し活」のコーナーでは、日本の8人組の男性グループ「MAZZEL(マーゼル)」を紹介しました。人間離れした精密なダンスやメンバーの素朴な人柄などが彼らの魅力です。今年2月にリリースした曲「J.O.K.E.R.」のダンス練習動画(Dance Practice)をまず見てほしいと岸田がお勧めしたところ、REINAさんも興味を持ったようで「ぜひ見てみたい」と話していました。【日経電子版の関連記事】■賃貸の火災保険、自分で選んで節約 必要以上の補償内容に注意■賃貸住宅、家賃抑える オートロックなし・築5年以上…

未来へつながる「クラウドファンディング」で心の満足感を
日経電子版「マネーのまなび」のPodcastです。アメリカ出身タレントのREINAさんがリスナーと一緒にお金のイロハを学んでいきます。解説は日本経済新聞編集委員の小栗太です。今回のテーマは「クラウドファンディングで心の満足感を」です。お金を儲けるだけの投資と異なり、「企業への応援投資」の性格を持つクラウドファンディングという新しい投資形態について学びましょう。番組では、小栗が東日本大震災のころから被災企業の支援策として注目されてきたクラウドファンディングの仕組みや種類を説明。金銭的な見返りを得る「出資型」や金銭的な見返りを求めない「寄付型」などがあり、大勢の人から小口の事業資金を集めることで「企業の成長やプロジェクトの成功への過程を、一緒に体感できることが大きな魅力になっている」と紹介しました。実は、REINAさんも利用経験者で、今年1月の米ロサンゼルスの山火事でもクラウドファンディングを通じて復興支援のための寄付をしたことを明かしてくれました。そのうえで「お金が増えた、減ったということばかりでなく、社会貢献など別の視点から投資を考えるのも大切なことですよね」と何度もうなずいていました。番組後半の「My favorite〜私の推し活」では、映画や音楽ではなく、家庭菜園を取り上げました。小栗が休日などに自宅の小さな庭で京野菜づくりなどを楽しんでいると話すと、REINAさんは「私も以前、イチゴを育てたことがあって、虫だらけになっていてショックを受けた」というエピソードを紹介。これからは野菜づくりにも挑戦したいと興味を持ったようでした。【日経電子版の関連記事】■未上場企業に個人も投資 投信・債券など手段も多様化■今更聞けないクラウドファンディング 実例で学ぶ11選■高配当株投資、株価下落での高利回りには注意

勝てる不動産投資と注目物件 REINAさんが産休明けで復帰!
日経電子版「マネーのまなび」のPodcastです。約3カ月間、産休中だったREINAさんが今回から復帰します。双子の女の子が生まれ、幸せいっぱいのREINAさんですが、「子育てをなめていた」と日々の育児は大変なようです。今回のテーマは「勝てる不動産投資」です。インフレ対策や家賃収入のため不動産投資に関心を持つ人は増えています。物件を安く買う方法や注意点を学びましょう。解説は日本経済新聞マネーのまなび面編集長の露口一郎です。不動産投資で得られるリターンは2つです。まずは安定した家賃収入。もう1つは値上がり益です。都心部を中心に不動産価格は上昇しています。このどちらを狙うかで、投資する不動産も変わってきます。高利回りの家賃収入を求めるなら、不動産価格自体が安い地方や郊外の物件が選択肢となります。一方、値上がり益を狙うなら、今後も人口の集中が見込める都心部の物件が選択肢となるでしょう。ただ、都心部の物件は「お値段がそれなりにしそうな気がします」(REINAさん)。安く買いたいなら、オーナーチェンジ物件が狙い目です。オーナーチェンジ物件とはすでに借り手が入居している物件です。マイホームを探している人が選ばないので価格が安くなりがちで、借り手の退去後に売却すれば値上がり益を得られる可能性があります。いい物件を見つけたら次はどうするか、番組では購入までの手続きも解説しています。後半の「My favorite〜私の推し活」のコーナーは、「効率的な筋トレ」を取り上げました。最近、露口は腰や肘の痛みに悩まされ、若いときにはできた筋トレができなくなっています。そこで最近はまっているのが「加圧トレーニング」。腕や脚の付け根に加圧ベルトをまきつけて血流を制限します。そうすると不思議なことに軽い重量でも筋肉に効いてきます。短時間で筋トレできるうえ、アンチエイジングや代謝促進などの効果もあるので忙しい人にもお勧めです。ただし、血流制限は体に負荷がかかり、貧血などのリスクがありますのでトレーナーなど専門家の指導を受けた上で取り組んでください。育児に追われてジムに行く時間がないREINAさんは「ちょっと試してみたい」と話していました。【日経電子版の関連記事】■自宅売却時の譲渡所得、所有期間で税率に違い■再建築不可物件も賃貸住宅に 空き家事業に挑むヤモリ

「高金利」預金の落とし穴に注意 抱き合わせ商法、仕組み預金…
日経電子版「マネーのまなび」のPodcastです。産休中のREINAさんに代わり、今週もお相手はフリーアナウンサーの宮島咲良さんです。解説は日本経済新聞の宮田佳幸です。今回のテーマは「『高金利』預金の注意点」です。6月になると夏のボーナスシーズンをにらんで、銀行が預金獲得のために様々なキャンペーンを展開します。「高金利」をうたった預金を用意して注目を集めようとすることも多くなりますが、その「高金利」には落とし穴があることも……。どんなところに注意が必要なのでしょうか。金利の高さをアピールする銀行がよく使う手法が「抱き合わせ」商法です。円預金の金利を高くする代わりに、外貨預金とセットにしたり、高コストの投資信託の販売とセットにしたりします。条件をよく検討して計算してみると、実はそんなにお得ではない、ということが少なくありません。デリバティブ(金融派生商品)を利用して高金利を実現する「仕組み預金」も、条件が複雑でわかりにくく、リスクが大きい割に得られるリターンが小さく、損をする可能性すらあります。宮島さんも「仕組みをよく理解できない金融商品には手を出さない方が賢明ですね」と気を引き締めていた様子でした。後半の「My favorite〜私の推し活」のコーナーでは、1982年公開の映画「ブレードランナー」を紹介しました。「人間とは何か」という重く哲学的なテーマを、暗く退廃的な未来都市の映像の美しさとともに描いた作品の魅力を宮田が熱っぽく語ると、「たぶんちゃんと見たことがないかも」という宮島さんも興味を持ったようで、「今回紹介されたのを機に、ぜひ見てみたい」と話していました。宮島さんの出演はひとまず今回で最後になり、次週からはREINAさんが復帰されます。【日経電子版の関連記事】■「高金利」うたう預金の注意点 適用の条件や期間に着目■「金利2%の円預金」の真実 プロも見誤った?カラクリ

プラチナNISAで「毎月分配型投信」が復活するのはなぜ?
日経電子版「マネーのまなび」のPodcastです。産休中のREINAさんに代わり、今週もお相手はフリーアナウンサーの宮島咲良さんです。解説は日経マネー編集長の武田安恵です。今回のテーマは「プラチナNISAと毎月分配型投信」です。2024年にスタートした新しい少額投資非課税制度(NISA)に、早くも見直しの議論が浮上しています。発端は4月15日の報道でした。26年度スタートを目指す形で、現行のNISAとは別に、65歳以上の高齢者が利用できるNISAの創設が検討されているというのです。そしてその「プラチナNISA」には、これまで長期の資産形成には適さないとして外されていた毎月分配型投信が、新たに対象商品として加えられるとか。なぜ、ここに来て加える動きになったのでしょうか。毎月分配型がなぜ問題視されるかというと、仕組みが複雑でリスクが高めの運用法を取ること、複利効果が見込めないことに加え、元本を取り崩して支払うものが多いことが上げられます。毎月分配型投信に限らず追加型株式投信の場合、先に投資を始めた人も、後から買って投資を始めた人も、口数当たりの分配金は同じです。投資期間が異なるのになぜ分配金を同じにできるのか――。ここで元本の取り崩しが出てきます。つまり投信の経理処理の仕組みを理解すれば、毎月分配型投信の問題点がよく分かるのです。武田の解説に対し、宮島さんも「仕組みは分かりましたが、ややこしいですね」と首をかしげていました。後半の「My favorite〜私の推し活」のコーナーでは「バラづくり」について紹介しました。武田は数年前からバラを育てており、趣味としてバラを育てている達人が多い中ではまだまだ若輩者ですが、ベランダに鉢植えを並べて若輩なりに丁寧に育てていました。しかし去年、部署異動や足のケガなどが重なって世話が十分にできず、なんとその多くを枯らしてしまったのです。美しいバラをだめにしてしまったことは後悔してもしきれない思いですが、中でも武田は「ハダニ」という害虫に悩まされました。ハダニがいかに面倒くさい害虫かを語り続ける武田に、宮島さんはひたすらうなずき、うまく話を引き出してくれました。【日経電子版の関連記事】■プラチナNISAは必要か 制度の信認揺らぐリスクも■プラチナNISA構想で「毎月分配型」投信に焦点
Create Your Podcast In Minutes
- Full-featured podcast site
- Unlimited storage and bandwidth
- Comprehensive podcast stats
- Distribute to Apple Podcasts, Spotify, and more
- Make money with your podcast