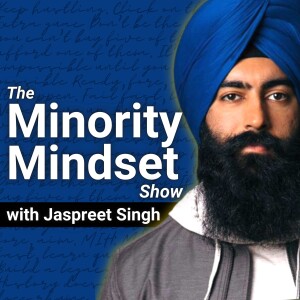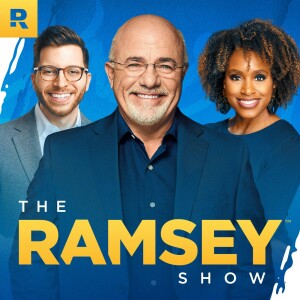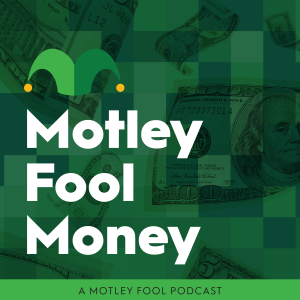REINAの「マネーのとびら」(日経電子版マネーのまなび)
https://anchor.fm/s/642771a8/podcast/rssEpisode List

賃貸住宅選びのコツ 「賢く妥協」すれば家賃は抑えられる
日経電子版「マネーのまなび」のPodcastです。アメリカ出身タレントのREINAさんがリスナーと一緒にお金のイロハを学んでいきます。解説はマネー報道グループの宮田佳幸です。 今回のテーマは「賃貸住宅選びのコツ」です。2〜3月は大学入学や就職、転勤などを控えて賃貸住宅を探す人が多くなるシーズンです。賃貸住宅の供給も増えます。一方で、賃貸住宅の家賃はかなり値上がりしています。家賃の負担をできるだけ抑えるにはどうしたらいいでしょうか。 一般的に賃貸住宅は、まず最寄り駅がどこか、そして駅までの所要時間がどれくらいか、という立地条件で賃料相場がほぼ決まり、生活と交通の利便性がいいほど高くなります。逆に最寄り駅までの所要時間がかかることなどを許容できるなら、家賃を抑えることは可能です。さらに、立地条件が同じでも、築年数や、物件の設備の違いなどで家賃に大きな差が出ることもあります。たとえば「オートロック」があるかないか、鉄筋コンクリート造か木造か、などの違いは家賃に大きく影響します。自分にとって優先順位の低い部分でうまく妥協できれば、年間で20〜30万円も家賃を下げられることもあるのです。 契約時に支払う敷金や礼金、仲介手数料、契約更新時の更新料、などにも注意しましょう。最近では契約時に連帯保証人を立てる代わりに保証会社と契約し、保証料を支払うことが必須の物件も多くなっています。番組では、賃貸住宅を探す際に注意すべき「おとり物件」についても解説しています。 番組後半のコーナー「REINAのFunny Japan」では、「小売店のポリ袋」について語り合いました。REINAさんは「日本では高級なスーパーほど、レジ袋を断っても店員が豆腐のパックをわざわざポリ袋に入れようとするなど、過剰包装になりがちな印象」と言います。宮田が「子どものころは豆腐屋さんが自転車で豆腐を売りに来て、買うときは家から鍋やボウルを持っていき、そこに豆腐を入れてもらっていた」と、自然にエコ活動ができていた昔の思い出話を披露すると、REINAさんはちょっと驚いた様子でした。 なお今回の「賃貸住宅選びのコツ」について、さらに詳しく知りたい方はこちらの日経電子版の関連記事もお読みください。 ■賃貸住宅、家賃抑える オートロックなし・築5年以上… ■賃貸住宅探しの基本 家賃は手取りの3割まで

ポイント"改悪"の傾向と対策 高額消費では支払い方を考えて
日経電子版「マネーのまなび」のPodcastです。アメリカ出身タレントのREINAさんがリスナーと一緒にお金のイロハを学んでいきます。解説はマネー報道グループの長岡良幸デスクです。 今回のテーマは「ポイント"改悪"の傾向と対策」です。買い物のおまけであるポイントの付与条件や還元率などのルールはしばしば変わります。最近の主な変更点や注意すべき点を押さえましょう。 最近ルール変更で話題になったのが、ネット通販の「楽天市場」で買い物をしたときのものです。楽天モバイルで特定の料金プランを契約すると手厚くなる一方、有料のクレジットカード利用などでは不利になるといった変更がありました。ネット通販の顧客をスマホ契約に誘導する目的とみられています。 マクドナルドでは店頭で特定のポイントカードを提示した際に付与していたポイントを廃止しました。REINAさんは「朝マック」がお気に入りだそうで「マクドナルド好きには影響が大きいかも」と話します。いわゆる新電力でもポイントの還元を縮小する動きがありました。 手間を掛けずに着実にポイントを受け取るためのコツは大きく3つあります。まずは「もらう機会を逃さない」。公共料金などはなるべく還元率が高いクレジットカードで払うように設定すれば、毎月ポイントがたまります。これからの引っ越しシーズンでは「手続きを忘れないようにしたいですね」とREINAさん。最近は投資信託の積み立てでポイントがたまるサービスも増えています。 2つ目が「高額商品はちょっと頑張る」です。ポイントの還元率を気にするのは、少額の買い物では努力に見合わないことも多いですが、数万円といった支払いでは還元率の差が大きく影響します。少し時間をかけてでも、最も有利な支払い方法を検討する価値はありそうです。番組ではこういった「誰でもできて効果的なテクニック」を紹介しました。 番組後半の「REINAのFunny Japan」は「パニックになりにくい日本人」をテーマに話しました。REINAさんによれば、日本人は大地震などの災害時でも落ち着いて助けを待っていることが海外メディアなどで称賛されているそうです。アメリカではハリケーンの被害があった後に略奪が起きたり、銃声が毎日聞こえたりするような地域があったといいます。この違いは、アメリカでは「自分の身は自分で守る」という意識の強い人が多い半面、日本では「誰かが助けに来てくれる」という信頼感があり、冷静に皆で助け合った方が早く復興できると分かっているからでは、という意見で一致しました。 なお今回の「ポイント“改悪”の傾向と対策」について、さらに詳しく知りたい方はこちらの日経電子版の関連記事もお読みください。 ■NISAの投信積み立て クレジットカードでお得に ■ポイント獲得、効率上げる 銀行・スマホ利用で上乗せ

知って得する投資家のための確定申告 「損益通算」で節税も
日経電子版「マネーのまなび」のPodcastです。アメリカ出身タレントのREINAさんがリスナーと一緒にお金のイロハを学んでいきます。解説はマネー報道グループの手塚愛実です。 今回のテーマは「投資の確定申告」です。2023年に株式や投信などの売買をした人に役立つ投資と税金の関係について解説します。 証券会社では、NISA(少額投資非課税制度)口座を除けば多くの人は「源泉徴収あり」の特定口座で運用しているので、株式や投信の売却益や配当、分配金から約20%の税金が自動的に差し引かれています。すべての口座がプラスであれば、確定申告の必要はありません。では、A証券の口座はプラスでもB証券の口座は大きくマイナスだったというケースはどうでしょうか。この場合、確定申告をすればA証券の口座で源泉徴収された税金が戻ってきます。これを「損益通算」といいます。 上場株式の配当は配当所得に該当し、3つの課税方法から選択します。所得水準によっては給与所得などと合わせて課税される「総合課税」を選んだ方が、適用される税率が下がる可能性があります。 その他、外国為替証拠金(FX)取引、ビットコインなどの暗号資産、金(ゴールド)と、金融商品によって「どの所得に該当するのか」が異なります。例えばFXは雑所得に分類され、会社員や年金受給者の場合、年間の利益が20万円を超えたら確定申告が必要になります。このように投資と税金の関係は非常に複雑。証券会社や国税庁のウェブサイトをじっくり見て、正しい知識を得たいものですね。 番組後半のコーナー「REINAのFunny Japan」は「日本の住所表記」がテーマでした。欧米ではほとんどの場合「番地+通りの名前」で住所を表示しますが、日本の住所表記に通り名はめったにありません。REINAさんによると、日本に来た欧米の人からは「わかりづらい、混乱する」といった声が聞こえるそうです。 日本は明治時代に「地番表示」を導入し、土地一筆ごとに番号を振りました。その後、1960年代に今の「住居表示」制度を導入し、町をブロックごとに分け、土地ではなく建物に番号をつける方式に変えました。ただ、全国一斉に導入したわけではなく、市町村によっては2つの仕組みが混在しているところがあります。こういった住所表記の不思議についてREINAさんと話し合いました。 なお今回の「投資の確定申告」について、さらに詳しく知りたい方はこちらの日経電子版の関連記事もお読みください。 ■投資の損失、確定申告で節税 利益と通算し課税減らす ■NISA、まず証券口座から 課税の有無や納税手段に違い ■所得税の節税、機会逃さず 外貨預金や株の利益確認

新NISAで人気化する高配当株 5つのポイントで銘柄選び
日経電子版「マネーのまなび」のPodcastです。アメリカ出身タレントのREINAさんがリスナーと一緒にお金のイロハを学んでいきます。解説は日経マネー編集長の中野目純一です。 今回のテーマは「新NISAで人気化する高配当株投資のノウハウ」です。この1月から始まった新しい少額投資非課税制度(NISA)の成長投資枠では、やはり高配当株が買われています。これは新NISAの開始前から予想されていました。非課税で投資できる期間が無期限化することにより、値上がり益だけでなくインカムゲインを狙った投資が格段にやりやすくなるからです。 新NISAが始まってまだ3週間余りですが、実際に高配当株に個人投資家の物色が集中しているもようです。SBI証券が同社サイトで公表しているNISA関連のランキングを見ると、成長投資枠で買われている銘柄の上位には、日本たばこ産業や三菱UFJフィナンシャル・グループなど、高配当株の定番銘柄がずらりと並びました。 一方、高配当株人気はここ3年ほど続いている強いトレンドなので、定番銘柄は既に買われて値上がりしていて、割高感が強まっています。全体相場にも過熱感がある中、ここからうかつに手を出すと、配当は受け取れても株価の下落でトータルではマイナスとなる恐れもあるのです。それを避けるには銘柄選びに工夫が求められます。どんな工夫が必要なのか、中野目編集長が具体的な5つのポイントや、実践する上での留意点を解説しました。 番組後半のコーナー「REINAのFunny Japan」では「ポケットティッシュ配り」を取り上げました。日本ではいろいろな企業が商品やサービスの販売促進策として、街角で無料でポケットティッシュを配っています。ただ、REINAさんによると欧米人は見知らぬ他人から無料で物を手渡されると警戒心を抱くため、この光景を見て一様に驚くそうです。ではなぜ日本でこうした販促手法が広がったのでしょうか。その経緯や、最近はこのティッシュ配りを目にすることが少なくなってきた背景などをひもときます。 なお今回の「新NISAで高配当株投資」について、さらに詳しく知りたい方はこちらの日経電子版の関連記事もお読みください。 ■新NISAで利点大きい高配当株 個人投資家も大注目 ■スゴ腕に聞く配当株投資のコツ IR資料の意外な活用法

増える日本企業のMBO 上場廃止で事業改革の道を探る
日経電子版「マネーのまなび」のPodcastです。アメリカ出身タレントのREINAさんがリスナーと一緒にお金のイロハを学んでいきます。解説は日経ヴェリタス編集長の島谷英明です。 今回のテーマは「MBO急増を読み解く」です。上場企業で経営陣が自社を買収するMBO(マネジメント・バイ・アウト)が増えています。なぜ増えているのか、また上場企業を取り巻く環境や株主にとってのメリットは何なのでしょうか。 2023年に発表されたMBOによる非上場化案件は計1.4兆円と、過去最大となりました。上場企業のPBR(株価純資産倍率)1倍割れを問題視する東京証券取引所が「資本コストや株価を意識した経営」を要請し、物言う株主と呼ばれるアクティビストも株価重視の要求を強めています。こうした中で中・長期的な事業の抜本改革に取り組むには、経営の自由度が高い非上場化が得策と考える企業が増えていると考えられます。 MBOでは一般的に、足元の株価に「プレミアム」を上乗せした高い価格で株式を買い付けることが多いため、既存の株主は売却益を得られる可能性があります。MBO予備軍と考えられるのは、創業家の持ち株比率が大きく、株価が低迷している企業です。ただ、実際にMBOを実行する企業を的中させるのは至難の業で、保有している銘柄でMBOが実施されることになったら「ラッキー」と思うくらいの姿勢が良さそうです。 MBO急増に表れている企業の資本効率改善の意識は、一段と強くなっていくと見られます。年明けから騰勢を強めている日本株が持続的に上昇していくには、企業が投資対象としての魅力を高めていくことが欠かせません。REINAさんも「株価につながる企業の動きについては、今年もしっかりウオッチしていきたいと思います」と話していました。 番組後半のコーナー「REINAのFunny Japan」は「助け合い」がテーマでした。REINAさんは、日本では米国と比べて困っている人が駅や街にいても自発的に手助けすることが少ないのでは、と感じることが多いそうです。これは一体なぜなのでしょうか。一方で近年は自然災害などの際にボランティアとして自ら被災地に向かう人も増えています。こうしたことを通じて、日本人の助け合い精神について考えてみました。 なお今回の「MBO急増」と関係する、最近の日本株についての詳しい解説を知りたい方はこちらの日経電子版の関連記事もお読みください。 ■個人マネーは日本株へ向かう
Create Your Podcast In Minutes
- Full-featured podcast site
- Unlimited storage and bandwidth
- Comprehensive podcast stats
- Distribute to Apple Podcasts, Spotify, and more
- Make money with your podcast